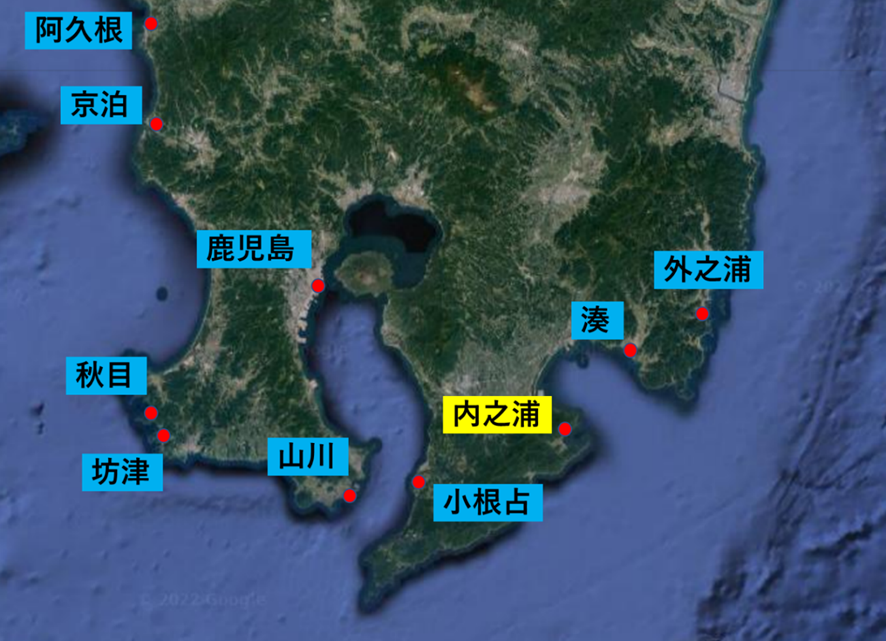鉄砲に比べ、大砲の国産化の方は難航している。大友氏が小型青銅砲の製造を行っていたようだが、銅はとにかく高価であったから、製造コストが非常に高くつく。代わりに安価な鉄で大砲を鋳造する、というのが世界的な代替手段なわけだが、日本においては難しかった。なぜか。
これは技術的要因、というよりも材料の質によるものだ。日本では古来より砂鉄などを原材料にした「タタラ銑鉄」により鉄を生産していたのだが、実はタタラにより得られた和鉄は、この種の鋳造に向いていなかったのである。
大砲製作に適した原材料は、ケイ素と炭素が適度に多く入っている鉄だ。柔らかく、靱性(じんせい)のある鉄――これを溶かして鋳造した結果、炭素が黒鉛化して出来上がりの表面が「ねずみ鋳造」と称されるほど、灰色になるのが理想なのだ。この鉄中に含有されている炭素が黒鉛化するのに有効な成分が、ケイ素なのである。
ところが、タタラ銑鉄で得られる和鉄を使うと、炭素とケイ素の含有量が共に足らず、どうしても「白鋳造」という、硬くてもろい――つまり破裂する危険性がある材質になってしまうのだ。これはタタラ銑鉄の持つ特性によるもので、比較的低温で行う精錬方法だった故による。精錬時の温度が低いと、炭素もだが、特にケイ素の含有量が低い鉄が銑鉄されてしまうのだ。
和鉄はこうした特性を持つ鉄であったから、大砲の鋳造に向いていなかった。その代わり、鍛鉄に向いていた。日本刀があそこまでの切れ味を誇ったのは、不純物の少ない和鉄の存在があったからだ。また同じ理由で、鍛鉄で造られる鉄砲生産にも向いていたのである。
上記のような理由もあって、戦国期において大砲は生産されなかったから、あまり活躍もしなかった。代わりに鉄砲の大型化を進めた「大鉄砲」が使われた。大鉄砲の大きさだが、概ね口径が20mm以上のものをそう呼んだようが、特に規格があったわけではない。呼び方もいろいろあって、大筒ないし持筒とも呼んでいた。いずれにせよ火縄銃と同じように構えて放つには大きすぎるから、両腕に抱え腰だめに放った。
大鉄砲は放った後、その衝撃を吸収するために、敢えて地面に転がることもあったようだ。こんなに凄まじい反動があって、腰だめで放って果たして的に当たるものだろうか。抱えるとなるとバランスを取る必要もあり、銃身も短くせざるを得なかったから、なおさらである。長篠の戦いの序盤で、武田方の攻撃を誘引するために織田方がこの持筒を使った、という説がある。鉄砲足軽数人を陣の前に並ばせて、勝頼本陣に向けて大鉄砲を放った、というものだ。当たらなくとも挑発することが目的だったとするならば、見事にその目的を果たしたといえるが・・
信長は大鉄砲を好んで使用している。伊勢長島の一向一揆攻め、九鬼水軍の木津川沖の合戦などで、艦載砲のような使い方をしている。こちらは挑発や威嚇だけに留まらず、実際に大きな効果をあげているわけだが、ちゃんと銃架に据えて使用したと思われる。残念ながら、口径などの大きさは伝わっていない。
更に巨大な大鉄砲として「慶長大火縄銃」がある。現存するものの中では最大級のもので、口径50匁(33mm)の玉を1600m飛ばせるというから、凄まじい。第二次大戦でソ連が使用した対戦車ライフルの口径が14.5mmだから、それの倍以上である。同じくドイツが使用した、大戦初期の対戦車砲の口径が37mmであるから、銃というよりも大砲に近い。

この大鉄砲をさらに、さらに大型化してみよう。するとあら不思議、本物の大砲の出来上がり。日本の鉄砲鍛冶職人は、鋳造が駄目ならいっそ鍛鉄で大砲を張ってしまえ、という荒業に出るのだ。
1611年に堺で張られた大砲「芝辻砲」は、長さ2m87cm・口径93mm・重量1.7トンという巨大なものである。構造・材質を分析したところ、砲身は8層構造になっていることが分かった。鉄片を張り付けて鍛鉄する作業を8回繰り返したということで、つまりは大鉄砲と同じ構造なのである。
家康は大阪城攻めのために、この大砲を発注したと伝えられている。そしてこの大砲を張ったのは、堺の鉄砲職人・芝辻理右衛門という男だ。彼は津田監物と一緒に西坂本で鉄砲を造った、あの芝辻清右衛門の孫なのである。
逆算すると、彼は西坂本で生まれ育ったはずである。根来寺の境内に遊びにいったこともあるだろう。幼少期を過ごした西坂本、そして根来を滅ぼしたのは秀吉であり、その血族である豊臣家に対して使われるこの大砲を、彼は張り切って造ったのではないだろうか。

日本の職人の鍛鉄技術は極めて高いレベルであったから、上記の大砲のみならず、他国なら鋳造するものまで鍛鉄で造ってしまった。葛飾北斎の浮世絵に、鍛冶職人たちが総がかりで巨大な錨を鍛造している絵が残っている。
和鉄による白鋳造だと、とにかく硬いものが出来上がってしまう。日常生活に使う小物ならまだしも、ここまで巨大なものだと、削る・くり抜く・曲げるなどの最終的な細工が難しかったから、鍛造してしまったのであった。(続く)